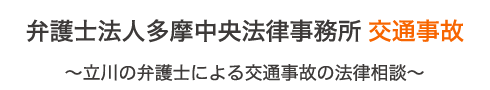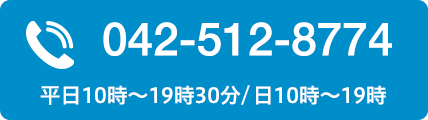Archive for the ‘未分類’ Category
【コラム】交通事故の損害賠償請求(人身)で争点になりやすいこと
交通事故被害の損害賠償の概要
交通事故の被害に遭うと、相手方本人に対して損害賠償を請求できますが、相手方に任意保険会社が付いていると、多くの場合、任意保険会社が代わりに交渉や支払いをします。(その他、労働関係における使用者や、加害者側の自動車の所有者に請求できる場合もあります)
その際には、人身損害としては、事故の損害に応じて、入通院慰謝料、休業損害、通院交通費、後遺障害慰謝料、逸失利益などの請求が可能です。ただ、必ず被害者の請求通りに支払ってもらえるわけではなく、相手方ないしその保険会社から反論を受けて争点となる場合があります。今回は、そのような争点になりやすい点について解説していきます。
治療期間について
以前にも解説しましたが、治療期間について争われることはよくあります。すなわち、事故による被害の治療として因果関係がある治療期間はいつまでか、ということが問題となります。ここで、症状固定という概念が重要となります。これは、これ以上治療を続けても症状が改善しなくなった時点を指し、それ以後は治療期間に含まれません。
治療期間が重要な理由は、2点あり、1点は、治療期間として認められた期間については治療費を請求できること、もう1点は、治療期間として認められた期間について入通院慰謝料を請求できること、です。
逆に言えば、症状固定後の治療費は原則自己負担となり(健康保険を使うことは手続きを踏めば可能)、慰謝料計算の期間にも参入されないことになります。
それゆえ、いつまでが治療期間か、ということは争点となることがよくあります。通院した期間が長い場合、特に途中から症状の改善が乏しい場合には、ある時点以後は因果関係がないという主張されることが多いです。そのような場合、被害者側の代理人は診療録(カルテ)などを根拠に反論していくことになります。
休業損害
休業損害についても、争われるケースが多いです。事故が原因で仕事を休んだ場合、それによる減収分(及び有給使用分)を加害者側に請求できますが、休業の必要性が問題となるケースが多々あります。すなわち、負傷の程度や回復具合に照らして休業期間の一部または全部について本来休む必要がなかったと主張されることがあります。
それ以外に、特に自営業の場合等には基礎収入の額や休業の事実について争われることも多いです。すなわち、自営業の場合は前年の確定申告をもとに基礎収入を計算するが一般的で、これに従った計算であれば通ることが多いのですが、売り上げの増加を反映させたい場合やそもそも申告が過少であった場合に実際の額で主張したいなど、上記と異なる方法で基礎収入を計算して主張すると、反論が出てくることが多いです。また、休業期間についても企業等に雇用されている場合と比べて立証が難しいという問題があります。また、休業の事実が認められても休業の必要性が問題になりうる点は同様です。
このように、休業損害は必ずしも主張通り認められるとは限りませんが、しかし、休みが長期の場合には金額も大きくなりがちであり、また、事故による生活への影響を補償する重要な制度なので、損害があった場合はしっかり主張することが重要だと思います。なお、負傷により身体的に就労できない日があった場合の他、通院のための欠勤・遅刻・早退でも認められることもあります。
なお、争われた場合には、当時の症状をカルテ等で立証しつつ、仕事の内容も含めて主張、立証して反論していくこととなります。
逸失利益
逸失利益は、後遺障害が残った場合において、症状固定後における就労能力低下による収入の低下のことを指します。14級なら5%、12級なら14%、等、後遺障害の等級に応じて労働能力喪失率の目安が定められています。労働能力喪失の率自体が争われることもなくもないですが、よく争われるのは期間です。すなわち、67歳まで、というのが原則ですが、むち打ちの場合にはより短い期間しか認められないことが多く、その際に、3年か5年か、ということはよく争点となります。被害者側としては基本的に5年で主張したいところですが、3年に限定する主張が加害者側から出てくることは珍しくないです。
その他、実際の減収がないということで認めない、あるいは一部しか認めない、というような主張がされることもあり、それに対しては、減収がないのは本人の努力によるものであるという反論が考えれます。
また、醜状障害について仕事内容を考えると影響がないはずという主張もよくありますが、これについては将来影響がある仕事に就く可能性もあるという反論が考えられます。
後遺障害慰謝料も比較的金額が大きくなりがちな項目であり、納得がいかない場合は、まずは交通事故に詳しい弁護士に相談して、妥当性について相談するとよいでしょう。
交通費
通院にかかった交通費も加害者側に請求できるのが基本です。それゆえ、合理的なルートであれば、鉄道やバスの運賃について争われることはあまりないです。自家用車のガソリン代(1km15円で計算)
しかし、タクシー代については、必要性が争われることも多いです。すなわち、電車やバスで通えたはずなので敢えてタクシーを使う必要はなかったという主張がされることがあります。これに対しては、怪我の程度や当時の症状などを主張、立証して反論していくこととなります。
過失割合
過失割合についても、争われることがあります。もっとも、一般道における追突の場合はほとんどの場合10:0で通りますし、それ以外の場合でも判例タイムズや赤い本にパターン別の基本的な過失割合と修正要素が出ているので、やみくもに争点化されるわけではありません。争われるのは事実認定の点が多いように思います。ただ、事実関係には基本的に争いがなくても、どちらに何割の過失があるかという評価をめぐって争点となることもあります。
最後に
このように、交通事故の損害賠償請求については、様々な点で加害者側の保険会社等に争われることがあります。そのような場合に被害者が充分な補償を受けるためには、専門的見地からの主張、立証が必要ですので、まずは弁護士にご相談ください。弁護士に御依頼の場合は、弁護士が知識や経験を生かして、代理人として交渉や訴訟を行っていきます。
当事務所では、交通事故の被害者側については相談だけなら無料、また、ご依頼の場合も着手金不要となっています。弁護士特約をご利用してのご依頼も歓迎します(なお、弁護士特約を使えるかどうかは、念のため、ご加入の保険会社に確認しておくことをお勧めします。なお、弁護士特約利用時の報酬基準は原則として保険会社の基準に合わせることとします)。
ご相談ご希望の方は、まずはお電話か電子メールでご予約ください。平日夜や日曜日の相談も可能です。
【コラム】交通事故被害者は労災で救済されるか?
1, 交通事故被害者が労災から支給を受けることができる場合
労災から支給を受けるためには業務上の災害により負傷したことが必要です。この点、私的な目的で移動中に事故に遭った場合は業務上の災害ではないので、労災から支給を受けることはできません。
一方、仕事中や通勤中に交通事故に遭った場合は、労災から支給を受けられる可能性があります。
2, 労災から支給されるもの、支給されないもの
労災はあくまで労働者の救済が目的です。そこで、交通事故の被害による損害のすべてを補償してくれるわけではありません。具体的には、治療費、休業損害、後遺障害がある場合の逸失利益、については補償がされますが、慰謝料は支給されません。それゆえ、慰謝料については加害者側に請求する必要があります。
また、休業損害は全額が出るわけではなく、元の給与の6割とされています(それ以外に特別支援金として2割が支給されるので実質8割もらえます)。逸失利益についても、労災からの支給は不十分であることが多く、それを超える部分は加害者側に請求することとなります。なお、7級かそれより重い等級の場合、労災からは年金方式で補償されるところ、相手方からの支給とは調整が行われます。
3, 労災の等級認定と自賠責の等級認定
労災も自賠責も建前としては等級認定の基準は同じとされています。しかし、実際には、違う等級が認定されることがあります。一般には、労災のほうが重い等級が認定される傾向があるといわれており、これは労災は労働者の救済を重視しているからだと考えられます。ただ、まれに、自賠責のほうが重い等級が認定されるケースもあるようです。異なる機関が認定するので、時には違いが出るのはやむを得ないでしょう。
4, 訴訟になった場合の自賠責の認定と労災の認定の違い
訴訟になった場合、自賠責の等級認定はそのまま裁判所にも認定してもらえる場合が多いです。例えば、自賠責で後遺障害14級とされたら裁判でも「赤い本」に従って14級の後遺障害慰謝料と、逸失利益が認定される場合が多いです。
一方、労災については、労働者救済のために緩やかに認定されていることは裁判所も理解しているので、必ずしもそのまま通用するとは限りません。しかし、後遺障害を認めるうえで有利な事実の一つとして労災の等級が挙げられる場合もあるので、労災の認定が訴訟で請求していく際に無意味というわけではありません。自賠責の等級が取れなかった場合でも労災の等級認定をとれたのであれば、訴訟をする場合は、主張の根拠として労災の等級認定の事実も主張するとよいでしょう。
5, まずは弁護士にご相談を
仕事中や通勤途中に交通事故に遭った場合、労災保険は心強い味方になりえます。しかし、労災だけでは不十分なのも事実です。なぜなら、労災は慰謝料を支払わないし、休業損害も満額は支給されないなど、必ずしも損害のすべてを補償する仕組みにはなっていないからです。そこで、不足分は原則として加害者に請求することとなるのですが、被害者の方本人で加害者や加害者側の保険会社と交渉することは、負担が大きいうえに、専門的知識の差で不利な示談を強いられることになりかねません。そこで、労災を利用できる場合であるか否かにかかわらず、交通事故の被害者の方には弁護士への相談をお勧めします。
弁護士に依頼すれば、交渉や訴訟は弁護士が代理人として行うので、ご本人様が相手方保険会社と直接やり取りする必要はなくなり、ご自身の精神的ご負担が軽くなるだけではなく、弁護士が専門的知識をもって交渉や訴訟に当たるため、法に従った充分な補償を受けることができると考えられます。特に、慰謝料については、「赤い本」に基づいた充分な補償を受けるためには、専門的知識に基づいた交渉が不可欠です。また、労災が先行している場合には、労災でどの項目がいくら支給されたかについて確認して、未支給のものについて加害者側に請求していくことになりますが、その確認していく作業も弁護士が行うことが可能です。(労災の資料取り寄せはご本人様にお願いしています)
交通事故の被害に遭われた方は、ぜひ、弁護士にご相談ください。当事務所では、交通事故案件に力を入れており、これまで多くの案件を扱ってきました。もちろん、被害者が労災からも給付を受けていた案件も多く扱っています。
交通事故に関しては、相談料は無料なので、まずは、ご相談いただければ、と思います。ご相談ご希望の方は、お電話か電子メールでご予約の上、立川の事務所にご来訪をお願いします。
なお、事故による負傷等の理由でご来訪が難しい場合、内容や事務所からの距離によってはWEB相談ができる場合もあるので、お問い合わせください
【コラム】非接触事故について
非接触事故とは?
交通事故において、加害者の車等とは衝突はしていないけれども加害者の車等の挙動が原因で負傷などの損害が生じたとされる場合があります。これを非接触事故といいます。
他の車の直前に割り込んだために割り込まれた車が避けるために進路を変更してガードレール等にぶつかった場合や、割り込みに対応して急ブレーキをかけざるを得ず、結果、乗っていた人が負傷した場合などが挙げられます。あるいは、オートバイの場合、衝突を避けるために急ハンドルを切ったら転倒した、など他車の運転が原因で転倒が生じて負傷したケースもあります。また、車と車に限らず、歩行者が自動車やオートバイの直前を横断したことで事故を誘発した場合も、同様です。
非接触事故における損害賠償請求
非接触事故でも損害賠償請求は可能でしょうか? 実のところ、損害が発生して、因果関係を示すことができれば、可能だと考えられます。すなわち、事故により負傷をしたこと、および、その原因が加害者の行動にあること、を示せれば、民法上、損害賠償請求が可能です。負傷の事実と、事故と負傷の因果関係が立証できれば、損害賠償請求の内容は一般の事故と同じです。個々の事情に応じて、治療費、慰謝料、休業損害、など各項目について加害者に請求していくことになります。
非接触事故で争点となりやすい点
非接触事故では負傷の有無、因果関係が問題とされやすいところです。すなわち、接触もしていないのだから衝撃はほとんどないはずなのに負傷をするのはおかしいという争い方をされることがあり、特に、相手方の車のみならず他の物との衝突もない事案ではそのような争い方をされる恐れが強いです。また、仮に負傷をしたとしてもそもそも相手方の車の運転が原因で急停車などの負傷の原因となる行為が生じたわけではないという争い方をされる場合があります。
たしかに、実際に衝突が生じた場合と比べると立証が難しいケースもありますが、裁判例を見ると、請求が認められたケースもあります。例えば、東京高裁平成30年8月8日(判タ1455号61頁~67頁)、さいたま地判平成30年5月31日、等は、非接触事故で負傷の事実及び因果関係を認定しています。
非接触事故でもまずは警察に届けを
非接触事故でも、事故である以上、警察への通報、負傷者の救護、が必要です(道路交通法72条1項)。また、警察に届けないと、事故証明も発行されず、加害者の責任を追及することが難しくなってしまいますので、その意味からも、警察への届け出は重要です。
非接触事故についての相談
非接触事故の被害に遭い、相手方保険会社等の対応に納得がいかない場合は、ぜひ、弁護士にご相談ください。弁護士は事件の依頼を受けた場合、代理人として相手方保険会社等と交渉をしたり、場合によっては訴訟を行ったりすることができます。非接触事故については保険会社との交渉が難航することが多いと思いますので、ぜひ、弁護士にご相談いただければ、と思います。
【コラム】相手方に任意保険会社が付いていない場合
任意保険会社が付いているとき
交通事故に遭ったとき、相手方に任意保険会社が付いていれば、その保険会社と示談交渉をするのが一般的です。なぜなら、任意保険には多くの場合、示談代行サービスが付いていて、加害者の代わりに被害者に対する補償について交渉する権限を持っているからです。弁護士に依頼した場合も、弁護士はまず相手方の任意保険会社と交渉するのが基本的な進め方となります。
任意保険会社が付いていないとき
では、加害者が任意保険に入っていない場合はどうすればよいでしょうか? その場合、まず、考えられるのは、加害者本人に直接交渉することです。もし、加害者本人に十分な資力があれば、これにより解決できる可能性も高いでしょう。
しかし、任意保険に入っていない場合、経済的にも余裕がないケースが多く、加害者本人が十分な賠償をできるとは限りません。その場合、どうすればよいでしょうか?
1, 加害者が業務中に起こした事故であれば使用者に請求する
もし、加害者が業務中に起こした事故であれば、使用者(会社など)に使用者責任を問うことが考えられます。この場合、使用者が保険に加入していれば、その保険から支払われることも期待できます。
2, 運行供用者責任を検討する
もし、加害者がほかの人の車を借りて運転していた場合は、貸していた側に対して運行供用者責任を追及できる可能性があります。ただし、人身損害に関してのみ、当てはまります
3, 上記1,2が難しい場合
しかし、使用者責任や運行供用者責任を追及できるケースは限られてきます。その場合、被害者はどうすればよいのでしょうか? まず、自賠責に被害者請求をすることが考えられます。任意保険に入っていなくても自賠責は入っているはずなので(入っていないと違法になってしまいます)、加害者の自賠責保険に被害者として請求をすることが考えられます。これを被害者請求といい、加害者の自賠責保険会社から書式を取り寄せ、必要な資料を集めて、同自賠責保険会社に提出することで、行うことができます。
ただ、自賠責保険は人身損害にしか使えず、また、金額的にも必ずしも満足をいく額にならないことが多いため、不足分と物損については加害者本人に請求することになります。
なお、自賠責保険では後遺障害の等級認定も可能なので、後遺障害があると考えられる場合は、特に、自賠責への被害者請求は重要になってきます。
まとめ
加害者が任意保険に入っていない場合でも、様々な工夫で、ある程度補償を受けることができるケースが多いです。加害者本人との交渉は一般の方には負担が重いと思いますが、当事務所の弁護士はそのようなケースについても経験を積んでいますので、ぜひ、ご相談ください。
【コラム】同乗者についても同じ弁護士に依頼できるか?(利益相反の問題)
利益相反とは?
弁護士は、ある依頼者の利益と他の依頼者の利益が対立する事件を受けてはいけません。例えば、一つの交通事故の加害者と被害者の両方から依頼を受けることはできません。なぜなら、依頼者の利益のために活動しないといけないところ、2名の利害が相反する人から依頼を受けた場合、片方の利益のために仕事をするともう片方の不利益になってしまうからです。
このコラムでは、上記の「利益相反」という問題について、交通事故の被害者側の車に同乗者(運転者以外に乗っていた人)がいる場合について、考えてみます。
交通事故の被害者に同乗者がいる場合
交通事故の被害者の車に同乗者がいた場合、その同乗者も加害者に慰謝料などの損害賠償請求ができます。この場合、追突など過失割合が10:0の場合は、そのまま加害者に請求すれば問題ありません。(追突でも例外的に被害者側にも過失がある場合は別途検討が必要です)
では、9:1、など、被害者側にも過失がある場合は、いかがでしょうか? この場合、同乗者の方は、過失割合に応じて加害者と被害者側の運転者に請求しても良いのですが、実は、全額をいずれかに請求することができます。なぜなら、双方に過失がある場合、双方の運転者は被害者に対して不真正連帯債務を負うと解されているからです。
なお、片方が全額を支払った場合は、支払った方は、過失割合に基づいてもう片方に求償の請求ができると解されます。したがって、公平は保たれると考えられます。
同乗者も同じ弁護士に依頼できるか?
では、被害者の車に同乗者がいた場合、同乗者も被害者(被害車両の運転手)とともに同じ弁護士に依頼して加害者に損害賠償請求をすることができるでしょうか?
実は、ここで、場合により、同じ弁護士への依頼が難しい場合があります。まず、被害者側に過失がない場合は問題ありません。例えば、追突された車に複数の人が乗っていた場合、弁護士はその全員から依頼を受けることもできます(例外的に追突された側にも過失がある場合を除く)。この場合、加害者側の車の運転手に損害賠償を請求することになります。それ以外に、使用者責任や運行供用者責任を追及できる場合もありますが、いずれにせよ被害者相互間の請求はありません。
また、被害者側の運転者にも過失がある場合でも、同乗者が家族の場合は基本的に問題ありません。なぜなら、家族内で互いに請求することは考えにくいからです。
しかし、同乗していたのが家族以外の場合、被害者側の車の運転者にも過失がある場合は、いずれ、同乗者から運転者へ損害賠償請求をすることになる可能性があります。前述の通り、同乗者は双方の運転者のいずれに対して請求しても良いのですから、被害者の側の運転者に請求することも考えられます。また、加害者側に請求して加害者が求償権を行使して被害者側の運転者に請求すれば、やはり、被害者側の運転者の不利益になります。そうすると、被害者側の運転者から依頼を受けている弁護士から見ると、自分の依頼者と利害関係が対立するとも考えられます。いわゆる利益相反です。そこで、このような場合、被害者車両の運転者と同乗者の両方から同じ弁護士が依頼を受けることは難しくなってしまいます。このような場合は、同乗者の方は他の弁護士に依頼することが望ましいと言えます。
同じ弁護士に依頼できる場合・できない場合(まとめ)
以上をまとめると、
被害者に過失がない場合・・・同じ弁護士に依頼できる
被害者に過失はあるが同乗者が家族の場合・・・原則として同じ弁護士に依頼できる
被害者に過失があり同乗者が知人や友人の場合・・・原則として同じ弁護士に依頼できない
となります。なお、これは原則であり、例外もありますので、まずは弁護士にご相談ください。
【コラム】後遺障害がない場合に依頼して費用で損をしませんか?
1,交通事故の補償の決まり方
交通事故の補償は、
・入通院慰謝料
・休業損害
・通院交通費
・文書代
・入院雑費
・付添い費
など後遺障害がなくても発生する(どの項目が発生するかは案件に寄りますが)ものと、
・後遺障害慰謝料
・逸失利益
など後遺障害がないと発生しないものに分かれます。
2,後遺障害がない場合の補償の金額
後遺障害がない案件でも、補償の額は怪我の程度などにより異なります。慰謝料は基本的に入院や通院期間が長いほど多くなりますが、怪我の程度により基準となる表が異なります(2種類あります)。また、通院だけより入院がある方が多くなります。休業損害は基礎収入(事故前の収入)と休業期間により決まります。
後遺障害がなくても、それなりに金額が多くなることはあり、例えば、赤い本Ⅱで計算する時(むち打ちで他覚所見がない場合など)に6ヶ月通院したら(入院がない場合)慰謝料は「赤い本」基準(裁判基準)で89万円となり、休業損害もあれば保険会社から支払われる額が100万円を超えることも珍しくありません。
3、後遺障害がある場合の補償額
後遺障害がある場合は、上記に加えて、後遺障害慰謝料と逸失利益が追加されます。後遺障害慰謝料は1級から14級までの等級に従って算出され、「赤い本」だと14級だと110万円、12級だと290万円、など、等級に応じて基準があります。一方、逸失利益は基礎収入に、等級に応じて決まる労働能力喪失率(14級だと5%、12級だと14%など)と、期間に対応するライプニッツ係数を乗じて決まります。
後遺障害慰謝料と逸失利益が加わる分、後遺障害がない場合よりかなり金額が大きくなります。
4,後遺障害がない場合でも弁護士に依頼して費用で損にならないか?
そうすると、後遺障害がない場合、比較的補償される金額が少ないのに弁護士費用を払うとかえって損をしないか、心配になる方もおられると思います。
・弁護士特約が使える場合
弁護士特約が付いていれば弁護士報酬を保険会社が払ってくれるので、ご自身が負担をすることはありません(弁護士特約の上限を超えるような大きな事故の場合は別ですが、後遺障害がない場合にそこまで大きくなる可能性はほとんどないと思います)。したがって、弁護士特約がある場合は、費用を気にせずご依頼頂くことができると思います。
弁護士特約はご家族のものが使えることもあれば、自動車保険以外の保険に付されていることもあるので、使えるかどうかよくわからないという場合は、契約している保険会社に問い合わせてみると良いでしょう。
・弁護士特約がない場合
弁護士特約がない場合ですが、「後遺障害がなく、かつ、裁判もしていない場合」は、当事務所の費用は成功報酬として「11万円(本体10万)+11%(本体10%)」となっており、後遺障害がある場合や訴訟をした場合の「22万円(本体20万円)+11%(本体10%)」より低く抑えています。
また、すでに提案がある場合は、増えた分のみを経済的利益として、経済的利益の8.8%(税込)(最低11万円(税込)を着手金、17.6%(税込)を成功報酬とする方式でご依頼いただくことができる場合もあります。
実際に依頼をしたことで得をしたかどうかというのは、提示後の御依頼の場合を除いてなかなか明確にはわかりにくいかもしれません。しかし、一般的に保険会社からの提案は慰謝料に関して自賠責とあまり変わらない場合も多く、任意保険会社内部の基準でも裁判基準と比べてかなり低いことが多いのは事実です。そうすると、一般には弁護士に依頼することで慰謝料が増額できることが多いということができます。また、弁護士に依頼頂ければ、相手方保険会社とのやり取りを弁護士が行うのでご本人様は相手方保険会社とやり取りをする負担がなくなること、法的に正当な額での補償を求めることができる、というメリットがあります。
もちろん、弁護士が入っても完全に希望通りの補償額になるとは限りませんが、「赤い本」の基準(裁判基準)に近いところで示談できることが大半であり(過失相殺による減額は別として)、また、休業損害の交渉も専門家が行うことで金額が増えることもあります。過失相殺の主張に関しても、弁護士は専門的見地からしっかりと主張をさせて頂きます。このように、解決へ向けた過程で専門家によるサポートを受けることができるというメリットがあるので、その点も含めてご依頼するかどうかは、ご検討頂ければ、と思います。
いずれにせよ、相談だけなら無料なので、まずはご相談ください。お電話か電子メールでご予約の上、ご来訪をお願いします。(負傷で動けないような場合には、電話相談やweb 相談での面談ができる場合もあります)
【コラム】事故車両の写真が必要となる場面
事故車の写真について
交通事故による損害の補償において、事故に遭って損害した自分の自動車の写真が必要になる場面がいくつかあります。この記事では、そういう場面について解説したいと思います。
物損に関して
まず、事故に遭った車を修理する場合、相手方保険会社と打ち合わせをしてから修理したほうが修理代を巡って揉めるリスクを避けることができるという意味で望ましいです。具体的には、相手方保険会社と修理工場で協議をして、協定を結ぶという作業が終わってから、それに従って修理をすれば、相手方保険会社から修理代の妥当性を巡って争われるという事態を避けることができます。そのための資料として、相手方保険会社は資料として事故車両の写真を送るように求めてくるのが一般的です。
また、全損扱いで廃車にする場合も、全損としての処理をして問題ないかの確認のために同様に写真を求められるのが一般的です。相手方保険会社から見ると、工場の見積もりだと修理代が車両価値を上回っていても、本当にそれで問題ないのか、確認するために写真を見たいということだと思います。
事故の態様や衝撃の証拠として
人身損害についての交渉や訴訟でも自動車の破損状況を示す写真が証拠として用いられることがあります。すなわち、傷の位置から衝突の態様を推測して過失割合算出の資料としたり、自動車の破損の程度から事故の衝撃を立証する、などの場面で事故に遭った車両の写真が必要になります。
事故車両の写真の撮り方
では、事故車両の写真を撮るとき、どのように撮れば良いのでしょうか? 目的によって異なる場合もあるので、ここでは物損の資料として用いる場合の一般的な要点について述べようと思います。物損の資料として用いる場合、①全体が写っている写真 ②損傷した部分の写真 ③ナンバープレートが写っている写真 が必要だと考えられます。今はデジタルカメラでの撮影が一般的であり、フィルム式カメラと違って多数撮影しても特にコストは増えないので、上記3点に気を付けつつ、多めに写真を撮って、しっかりと記録を残すと良いと思います。
なお、交渉や訴訟で証拠として用いるということを考えると、写真はできる限り早く採る方が良いと思います。なぜなら、事故から時間が経ってから撮影すると、もし傷があっても、その後に損傷したのではないかと主張される恐れも出てくるからです。
事故車の修理費用を巡って困っている方はご相談を
事故車の修理費用について、相手方保険会社との交渉に困っている、悩んでいる、という方は、ぜひ、弁護士にご相談ください。保険会社との交渉などのやり取りを被害者の方に代わって弁護士が行うことができます。
【コラム】被害者の過失・・相手方への支払い義務が生じうることに気を付けよう
過失割合とは?
過失割合は、ある事故について、どちらの当事者にどれだけの比率で過失があるか、という割合のことです。例えば、信号待ちで止まっている車に後続車が追突すれば、原則として10:0で後続車に過失が認められます。あるいは、直進している車と隣の車線からの進路変更の車が衝突した場合は、原則は進路変更車が7,直進車が3,の過失として、7:3の過失割合となります(ただし、速度違反、脇見運転、酒気帯び、などの事情により変動します)。
このように、個々の事故について、各当事者の責任の割合を決める必要があります。
過失割合は誰が決めるか?
過失割合は、交渉であれば、両当事者の合意で決めれば良く、裁判の場合は、判決まで進める場合は裁判所が判断します。裁判でも途中で和解をする場合は、当事者間での合意に従って、ということになります。
被害者の過失と相手方への賠償
被害者にも過失がある、となると、もらえる損害賠償の額が減ってしまう、ということがまず思い浮かぶと思います。例えば、後遺障害等級14級の慰謝料は「赤い本」だと110万円だけども、被害者にも1割過失があれば、1割減って99万円になってしまう、通院6か月の通院慰謝料は「赤い本」表2(軽度のむち打ちなどの場合用の表)だと89万円だけども過失1割だと約80万円に減ってしまう、というようなイメージを持つ方も多いと思います。
それは間違ってはいません。もっとも、損害賠償は慰謝料だけではなく、治療費、休業損害、逸失利益、交通費、文書代、など案件によりますが様々な項目があるので、それを合計した額を損害額として、そこから被害者側の過失分を差し引くという方法を採るので、すでに満額でもらっている項目がありそれが多額だと、これから請求できる分が思ったよりも少ないこともありますので、注意が必要です。
ただ、ここで気を付けたいのは、単に請求額が減るだけではないということです。すなわち、被害者側にも過失があるということは、相手方に損害があれば、その損害を過失割合に応じて補償しないといけないということです。もし、被害者が歩行者で、加害者が四輪自動車の場合、自動車に乗車中の人に負傷が生じるケースは少ないですし、自動車が損傷することも少ないと思います。そうすると、仮に歩行者側にも過失があったとしても、その請求できる損害賠償の金額が減るだけで済むことがほとんどでしょう。
しかし、四輪車どうしの事故や、バイクどうしの事故、あるいは、四輪車とバイクの事故、では双方に乗車している人の負傷や車の損傷が生じることが珍しくありません。そうすると、被害者といえども、過失があれば、相手方に生じた損害を賠償する義務を負ってしまうのです。
例えば、四輪自動車同士の事故を考えてみましょう。A車が駐車場から本線に進入してきたときに本線を走行していたB車と衝突して起きた事故で、過失割合はAが8,Bが2,だとします。すなわち、過失割合は本線を走行していた車が2,進入しようとしていた車が8,ですが、ここでは、進入しようとしていたA車は横から衝突されたために人・車ともより大きなダメージを受けたと仮定します。
ここで、Aは負傷し、治療費や慰謝料など300万円の損害を受けたとします。A車も損傷し、修理代など物損は50万円とします。そうすると、A側の損害は合計350万円なります。一方、Bは負傷しましたが後遺障害はなく治療期間も短かったため損害は治療費や慰謝料など合計しても70万円、B車の物損は修理代として20万円、合計90万円の損害だとします。
そうすると、基本的にBが被害者といえるでしょう。そこで、BはAに対して、損害90万円のうち8割の72万円を請求できることになります。では、Aからみるとどうでしょうか? 損害350万円のうちBの過失に相当する2割、すなわち、70万円分をBに請求できることになります。
そうすると、もともとの過失はAのほうが大きいのに、互いに請求できる額はほとんど同じになってしまいます。
これは少し極端な例ですが、被害者だと思っていても、相手方の損害が大きいと、それなりに賠償しないといけないことがあります。もっとも、自分の責任分には自分の保険を使えれば実際に支出するわけではなく、人身損害については一定範囲で自賠責保険も使えますが、自分の任意保険で支払ってもらう場合には保険料が上がるなどのデメリットもあり、示談交渉をするときには、被害者側であっても、相手方の損害の有無と過失割合には留意する必要があります。また、改正民法では、人身損害について相殺できないのは従前と同じですが(509条2項)物損分については相殺することも可能なので、その点にも注意が必要です。
なお、これに関連して、9:0という不思議な過失割合で示談するケースがあります。これは、被害者側にも1割の過失があるとも思われる場合に、被害者は自身の損害賠償請求額が本来より1割減ることは受け入れる代わりに、相手方の損害への賠償はしない、という形で示談をすることを言います。早期解決のための工夫であって、訴訟の判決でこのような解決になることは考えにくいところですが、示談交渉では行われることがあります。
まとめ
被害者側にも過失がある場合、相手方にも損害があれば、原則として過失割合に応じた損害賠償義務があることになります。そこで、示談交渉をする際には、そのことも念頭に交渉を進めていく必要があります。
過失割合については、「判例タイムズ38巻」や「赤い本」に基準が出ており、おおよその計算方法は示されていますが、事実認定やその解釈を巡り、争いになりやすい部分でもあります。もし、相手方本人や相手方保険会社から示された過失割合に納得がいかない場合は、まずは弁護士にご相談ください。
【コラム】自動車と道路を横断する歩行者の事故の過失割合
自動車と横断歩行者の事故
ここでは、横断歩道や交差点以外の場所で、道路を横切ろうとしていた歩行者と道路を走ってきた四輪自動車が衝突した場合の過失割合について検討します。交差点付近や横断歩道付近でもなく、一本道を横切るような場合を想定しています。
基本的な過失割合
この場合、基本的な過失割合は、自動車8:歩行者2、です。(判例タイムズ38巻図【37】)
一般に、自動車と歩行者の事故だと車の責任が重くなるという印象があると思いますが、たしかに、この場合、車の方の責任が重いのが原則です。自動車を運転する時には、歩行者が道路を横切ることも想定して注意しながら運転することが求められていると言えます。
もっとも、歩行者にも2割の過失が設定されており、歩行者にも道路を横切るときには自動車が来ないか注意することが求められているということができます。
ただし、以下のように、過失割合が修正がされる場合があります。
修正要素
修正要素としては、歩行者側の過失割合を増やす方向のものとして、
- 夜間 5
- 幹線道路 10
- 横断禁止の規則あり 5~10
- 直前直後横断・佇立・後退 10
があります。
タイズム38巻第1章の解説によると、夜間は日没から日の出までを指すとしたうえで、一般道路ではトンネルの中や濃霧で視界が50m以下の場合は同様に解してよいとされています。
また、幹線道路については、歩車道の区別があること、車道幅員が概ね14m以上(片側2車線以上)、車両が高速で走行すること、が要素として挙げられ、通行量の多い国道や都道府県道を想定している、としています。
横断禁止の規則あり、については、横断が禁止されているのみならず、歩車道の区別や標識、ガードレール、フェンス等の設置、などにより横断禁止であることが容易に認識できることも前提とされている、とされています。
直前直後横断については、道路交通法13条1項で禁止されているということが上記解説では理由として挙げられており、斜め横断も12条2項で禁止されているので同様に歩行者側に不利に働く、と指摘されています。
これらを検討すると、まず、夜間は車から歩行者が見えにくいので、より歩行者が注意をする必要性が高いでしょう。また、幹線道路についても、幅が太く車が多い道は自動車の走行の利便を重視して造られており、敢えて横断する場合、歩行者はより注意を払うことが求められていると考えられます。
また、横断禁止の場所の横断や直前直後の横断等は、道交法違反である以上、本来行うべきではないことを敢えて行なったということで、過失が重くなるということだと思われます。横断中にその場で佇んだり、敢えて後退するようなことも危険を増すので、加算要素になっていると考えられます。
このように、歩行者の過失は、基本は2割ではあるものの、夜間、幹線道路、道交法違反などを伴う横断の場合には過失が加算されること、がわかります。また、それぞれの加算要素は複数ある場合、足し合わせることに注意が必要です。例えば、夜間に幹線道路を横断禁止を無視して車の直前を横断しようとして事故に遭ったとすると、30~35の修正となり、歩行者側の過失減算要素がなければ、歩行者側の過失が50~55%になってしまいます。
もちろん、実情に応じて修正されうるので、必ずこの図の通りに修正されるとは限らないのですが、場合によっては、概ね5:5ないしより歩行者に不利なところまで修正されうることは念頭に置いておくと良いと思います。
一方、歩行者側の過失を減らす修正要素としては、
- 住宅街・商店街等 -5
- 児童・高齢者 -5
- 幼児・身体障害者等 -10
- 集団横断 -10
- 車の著しい過失 -10
- 車の重過失 -20
- 歩車道の区別なし -5
となっています。
上記の用語に付いて、タイムズの解説は、まず住宅街・商店街等、は人の横断・通行が激しいか、または頻繁に予測される場所を想定していて、人通りの絶えた深夜の住宅街・商店街等や、郊外の住宅・商店が間隔を空けて存在する場所は含まない旨を述べています。つまり、人の横断・通行が激しい場所や頻繁に予測される場所では、自動車の運転者は横断者が現れることをより容易に予測できるはずなので、より注意すべきである、ということで、歩行者側の過失割合の減算要素(車から見れば加算要素)とされているのだと解されます。
集団横断については集団登下校を例として挙げており、数人が外形的にみて同様の行動をしていれば足りる、としています。これについては、みんなで渡るなら十分注意しなくても良い、というわけではなく、自動車側から見て気づきやすいはずなので、それにもかかわらず衝突に至った場合は自動車側の過失が重くなるということだと考えられます。
児童・幼児、については、道交法14条3項に定義があり、児童は6歳以上13歳未満の者、幼児は6歳未満の者、とされています。高齢者については、道交法に明確な規定はありませんが、タイムズの解説では、概ね65歳以上とされています。これらの者については、判断能力や行動能力が低いので特に保護する必要が高いがゆえに、その能力に応じて2個のカテゴリーに分けて過失を減算することにした旨、解説は述べています。幼児のほうが児童より年齢が低いので、より強く保護する趣旨で、減算が大きくなっています。なお、直接当てはまらなくても社会的要請によっては同様に減算要素となりうる場合があるとされています。
また、歩車道の区別のある道路かどうか、については、おおむね1m以上の幅の路側帯の有無で判断されます。
また、車の側の著しい過失は時速15km以上30km未満の速度違反、脇見運転、携帯で話しながら運転したり画面を見ながらの運転、などが例示されています。
また、重過失は、さらに過失が重い場合であり、酒酔い運転、居眠り運転、時速30km以上の速度違反、などが挙げられています。
上記をまとめると、現場の状況や道路構造に関する要素、歩行者の属性に関する要素、横断方法に関する要素、車の運転方法に関する要素、があり、それぞれ歩行者の過失を減らす要素となっています。
上記を前提に考えると、例えば、児童が集団登校中に道路を横断していて事故に遭った場合、他の修正要素がなければ、車95歩行者5の過失割合になる、ということになります。もし、その場合で、歩車道の区別がなければ、10:0で車の過失ということになります。
もっとも、歩行者側に加算要素があれば異なってきます。例えば、上記の例で集団登校州の児童が道路を渡りながらふざけていったん渡りかけた道路を後戻りしたりすると、歩行者側の過失が10増えるため、車90歩行者10になると考えられます。直前直後横断も同様です。
こう考えると、集団登校の児童を見つけた自動車の運転者には高度な注意が求められている一方、児童も道を渡るときは交通法規を守り、敢えて危険なことはしないようにすることが求められていると言えるでしょう。
まとめ
以上のように、道路横断の際の事故は、基本的には、自動車の過失が8割、歩行者の過失が2割、とされますが、様々な要素により修正されます。実際の交渉では、過失や重過失の根拠となる事実の有無の他、事故の現場が歩車道の区別がある場合や、幹線道路、商店街・住宅街等、に当たるか、あるいは、横断の態様が集団横断と言えるかどうか等、事実の評価を巡って争われる場合もあります。弁護士は、依頼者からの聞き取り、実況見分調書、ドライブレコーダーや防犯カメラ、現場の確認、その他、事案に応じて様々な手段で事実関係を把握し、証拠を集めるとともに、法律や判例(および、それを元に作られた「赤い本」や「判例タイムズ38」など)に当てはめて解釈し、相手方との交渉や訴訟に当たります。過失割合については、事実関係の調査、その当てはめ、いずれにおいても複雑な作業が必要なので、専門家の力を借りる必要性が高いと思います。
また、歩行中に車に衝突された事故の場合、たいていの場合は自分の側は賠償責任を負わないため、そうすると、自動車同士の出会いがしらの事故のように自分の任意保険の示談代行を使うというわけにもいきません。それゆえ、弁護士に相談、依頼する必要性は高いと思います。
交通事故の過失割合を巡る問題は、当事務所でも多く扱ってきました。もちろん、道路横断時の過失割合が関係する事案も扱ったことがあります。道路横断時の事故の過失割合について、加害者やその保険会社の対応に納得がいかない場合は、まずは弁護士にご相談ください。
【コラム】当事者尋問の進め方
当事者尋問とは?
当事者尋問とは、裁判の当事者、すなわち、原告か被告を裁判所に呼んで尋問することを言います。証人尋問という言葉を聞いたことがある方は多いと思いますが、民事訴訟法では、第三者を尋問する手続きを証人尋問、当事者を尋問する手続きを当事者尋問と呼んで、区別しています。
当事者尋問の内容は、調書に記録され、証拠となります。ただし、交通事故訴訟でいえばドライブレコーダーの画像や防犯カメラの画像のように客観性がある証拠と比べると、証拠としての力が弱いという面はありますが、裁判官が当事者の供述を直接聞くことができる手続きであるため、重要な証拠方法であることに違いはありません。また、陳述書のように一方的に述べたものと異なり、相手方による反対尋問の機会が保障されているため、証拠としての力はそれなりにあるとも言えます。
なお、当事者尋問は、民事訴訟一般に用いられる手続きですが、この記事では交通事故に関する民事訴訟を念頭に解説を書いていきます。
どのような場合に当事者尋問が行われるか
物証(物が証拠になる場合のその証拠をこのように呼びます)のみでは争点についての判断に不十分だと思われるときで、当事者の認識している事実が争点の判断において意味を持つと思われる場合に行われます。交通事故訴訟だと、過失割合、休業の必要性、後遺障害の実態、慰謝料の額の相当性、など様々な争点について、行われることがあります。もちろん、複数の問題について、事実関係が質問対象となることも珍しくありません。
なお、当事者尋問の実施は、裁判所が一方的に決めるのではなく、当事者が申請して裁判所がそれを認めるという形で行われます。
当事者尋問の事前準備
当事者尋問は法廷で行われますが、その成否は、実はそれ以前の準備の段階である程度決まっていると言っても過言ではありません。すなわち、事前の十分な準備がなければ、当日、自分の側の当事者から良い証言を引き出すことはできず、また、何が問題かを把握していなければ、反対尋問で効果的な質問をすることもできないからです。
では、事前の準備はどのように行うのでしょうか? ここでは、交通事故被害者の視点で記事を書いていますので、当方が原告だと想定します。まず、当事者尋問を行う場合、事前に陳述書を出すのが原則です。その陳述書は、それ自体証拠となるものですが、それに基づいて尋問を行います。(この点は以前の記事に書いた通りです)
陳述書の内容は当然、本人が経験した事実を書くのですが、何に触れるべきか、どの程度具体的に書くべきか、など書き方については弁護士からアドバイスをします。そうして、出来上がった陳述書や、尋問事項書等を確認しながら打ち合わせを行います。
まず、一般的な説明として、「法廷での証言なので、必ず、記憶の通り答えてください。覚えていないときは、覚えていないと言ってください」ということと、「一問一答なので、聞かれたことにそのまま答えてくださいね」という原則を説明し、それから、具体的に、どういう内容について聞く予定かを説明し、必要に応じて、リハーサルのようなことも行います。このような形で準備をしておかないと、当事者は、いきなり聞かれたから答えられなかった、あらかじめ言って欲しかった、というようなことになりかねません。それゆえ、事前の打ち合わせは重要です。
同時に、相手方の陳述書も来ているはずなので、弁護士はそれについても検討します。ここでは、反対尋問で何を聞くべきか、を、どの事実が相手方の主張の根拠になっているか、ということから考え、それを崩すにはどうすればいいか、と考えて反対尋問の質問内容を考えます。そうして、当日に、供述の矛盾や客観的事実との不一致を導き出せれば、相手の供述の信用性は揺らいだと言えるでしょう。また、重要な事項について相手方の回答が曖昧な場合も、やはり、信憑性の低さを印象付けることに成功したと言えるでしょう。この辺りは弁護士の技術であり、基本的に当事者の方に考えていただく部分ではないので、ご安心ください。
当事者尋問の流れ
当事者尋問の当日は、まず、
原告に対して
主尋問 →反対尋問 →補充尋問
の流れで行われ、その後、
被告に対して
主尋問 →反対尋問 →補充尋問
という流れで行われるのが基本です。
主尋問は、それぞれ、その当事者の代理人弁護士が行い、反対尋問は相手方の代理人弁護士が行います。補充尋問は、裁判官による尋問です。
当事者は、メモなどの文書を見ながら回答することは例外的な場合を除いて認められません。あくまで、ご自身の記憶にあることを答える必要があります。
時間は、ケースによりますが、それぞれ、1時間を超えることはまずありません。あらかじめ、主尋問20分・反対尋問20分、などという形で時間は制限されます。(上記時間は一例です)
主尋問は、自分の側の弁護士が行うのであり、あらかじめ何を聞かれるかは打ち合わせてあるわけですから、あとは、記憶の通り回答するだけであり、それほど難しくないと思います。
問題は、反対尋問です。反対尋問は相手方の弁護士が、あなたの証言の信憑性を崩すために行います。そして、反対尋問で具体的に何をどのように聞かれるかは、相手方の弁護士以外は知らないわけです。それゆえ、何を聞かれるかわからず不安、という方も多いと思います。ただ、反対尋問は主尋問の範囲に限定されるので、実際のところは、何を聞かれるのか全く分からないというわけではありません。相手方の代理人弁護士は、あなたが提出した陳述書や当方の代理人が提出した尋問事項書を参考に反対尋問で触れることを決めているはずであり、主尋問で聞かれていない全く関係ないことを聞かれることは基本的にありません。ただ、主尋問で聞かれた事項の他に、証言の信用性に関する事項も訊けることになっているので、突然関係ないことを聞かれた、と感じることもあるかもしれません。全く無関係な質問やその他民事訴訟規則で禁じられているとも受け取れる質問であれば代理人が異議を述べることもありますが、そうでなければ、慌てずに、記憶しているところを答えて頂くということになります。
当事者尋問の後
当事者尋問は、それを元に調書が作成されます。調書には尋問内容が文字化して記載されており、これは証拠となります。証拠にするために特に手続きは必要なく、その後準備書面を出す場合は、そのまま引用することができます。(ただ、当日終結のことも多いです)
*なお、簡裁の場合は調書作成が省略されることもあります。
また、当事者尋問を行なった日は、双方の当事者がそろっているということで、和解の話し合いが行われることも多いです。和解が成立すれば、そこで裁判は終わります。
和解が成立しなければ、尋問後は、それほど期日を入れずに結審となることが多いです。なぜなら、尋問は双方の主張が出尽くした後に行われるのが基本だからです。もし、早い段階で尋問をしてから争点が出てきたら、それについて再度尋問を行うのかということになり、効率が良くないので、そういうことはせず、双方の主張が出そろってから最後のほうに行うことになっています。
まとめ
当事者尋問は客観的な証拠と比べると証拠としての力は強くはないと考えられますが、反面、裁判官が直接当事者から話を聞いて心証を得る事ができる貴重な機会であり、案件によっては、結果に影響を与えることは充分にあり得ます。それゆえ、事前に弁護士とよく打ち合わせて、充分準備をした上で臨みましょう。
« Older Entries Newer Entries »