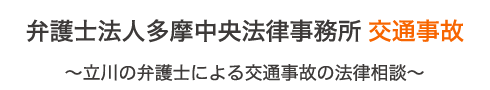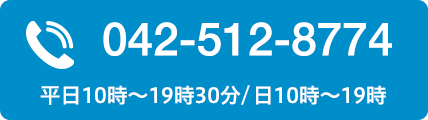このページの目次
後遺障害に対する損害賠償について
後遺障害に対する損害賠償として、代表的なものは、後遺障害慰謝料と逸失利益があります。後遺障害慰謝料は後遺障害が残ったことに対する慰謝料であり、一方、逸失利益は後遺障害で労働能力が一部または全部喪失したことに対する補償です。したがって、これらは後遺障害に対する補償ではありますが、性質が異なります。なお、これ以外に重度の後遺障害の場合は介護費用が認められる場合があります。
後遺障害慰謝料とは
後遺障害慰謝料は後遺障害が残ったことによる精神的苦痛に対して認められる慰謝料であり、入通院慰謝料とは異なります。入通院慰謝料は交通事故により負傷をしたこと自体に対する慰謝料なので、後遺障害が残らなくても認められますが、後遺障害慰謝料は後遺障害が残らないと認められません。ただ、自賠責の後遺障害認定が不可欠かというと、認定されなかった場合でも、訴訟で立証できれば支払ってもらうことができます。もっとも、自賠責による後遺障害認定を得られれば交渉でも支払ってもらえることが多く、訴訟にした場合でも裁判所に認めてもらいやすいので、通常は、まずは自賠責(損害保険料率算出機構)の認定を申請する(任意保険会社を通す方法と、自賠責への被害者請求の2通りがあります)のが一般的です。
後遺障害慰謝料は、「赤い本」に基準が出ており、例えば、14級だと110万円、12級だと290万円、となっています。この基準に沿って認められることが多いですが、具体的事情による増減はあり得ます。 また、交渉の場合は、相手方保険会社は必ずしも赤い本の基準の満額を支払ってくれるとは限らず、9割程度の額までしか提示してこないこともあり、そういう場合には、交渉を尽くしても満額の提示が得られない場合には、妥協するのか訴訟をするのか、という決断が必要になります。
逸失利益とは
逸失利益は、後遺障害により労働能力の一部または全部を喪失した場合に認められます。一部喪失の場合は、その割合に応じて計算されます。労働能力喪失の割合は後遺障害の等級に基づいて基準があり、例えば、14級だと5%、12級だと14%とされています。具体的な計算としては、「基礎収入」×「労働能力喪失率」×「ライプニッツ係数」で算出します。ライプニッツ係数は労働能力喪失の期間に応じて決まります。労働能力喪失の期間は、通常、67歳までとされていますが、むち打ちで14級の場合には一般に5年程度とされることが多い、など、例外もあります。
もっとも、これはあくまで基準であり、必ずその通り認定されるわけではありません。なぜなら、逸失利益は労働能力の低下による損害を補償するためのものであり、理論的に考えると、後遺障害があっても労働能力の低下がなければ発生しないことになるからです。この点に関して、よく争われるのが醜状損害です。職種によっては見た目に傷が残っても仕事の能力に影響するとは限らず、認められない場合もあります。また、認定された等級に基づく基準より少ない労働能力喪失率しか認められない場合もあります。
ただ、逸失利益を認めない代わりに慰謝料を通常より増額した判例もあり、仮に労働能力の喪失が認められなくても慰謝料の額の決定において考慮される場合もあるといえます。
醜状損害以外でも、実際の減収がない場合には、労働能力喪失がないのではないか、という主張が加害者側の保険会社から出る場合もあり、それに対しては、労働能力の低下を補うために特別な努力をしたり追加で費用をかけた結果売り上げが維持できたのであって労働能力の喪失は生じているということを主張する、など反論が必要です。
もちろん、どのケースでもそのような問題が生じるわけではなく、等級認定に従った計算でそのまま合意できることもあります。
後遺障害慰謝料と逸失利益の違い
後遺障害慰謝料は、後遺障害等級認定が取れれば、比較的等級認定に基づく基準に概ね従って認めてもらえるケースが多いと思います。もちろん、事情により増額を主張したいケースはありますが、比較的基準に近いところで解決するケースが多い印象があります。後遺障害が残ったことによる精神的苦痛を金銭に換算するものであり、等級認定が取れれば、その等級に従って算出されるのが一般的です。したがって、大半のケースでは、「赤い本」の等級の通りの金額での示談を目指しての交渉となります。
一方、逸失利益は後遺障害により労働能力が低下して将来の収入が失われたことについて補償する趣旨であるところ、収入の低下の有無、事故直後の休業の有無、障害の部位や内容、によっては争われるケースも珍しくありません。また、被害者の側から見ると、職業柄、通常より影響が大きい場合もあり(重い荷物を扱う仕事の人がむち打ちで後遺障害が残った場合、など)、そのような場合には労働能力喪失率や喪失期間について通常より被害者により手厚い補償が支給される方向での主張ができる場合もあります。そういう意味では、個別性が強い問題であり、丁寧な立証が求められる場合が多いといえるでしょう。